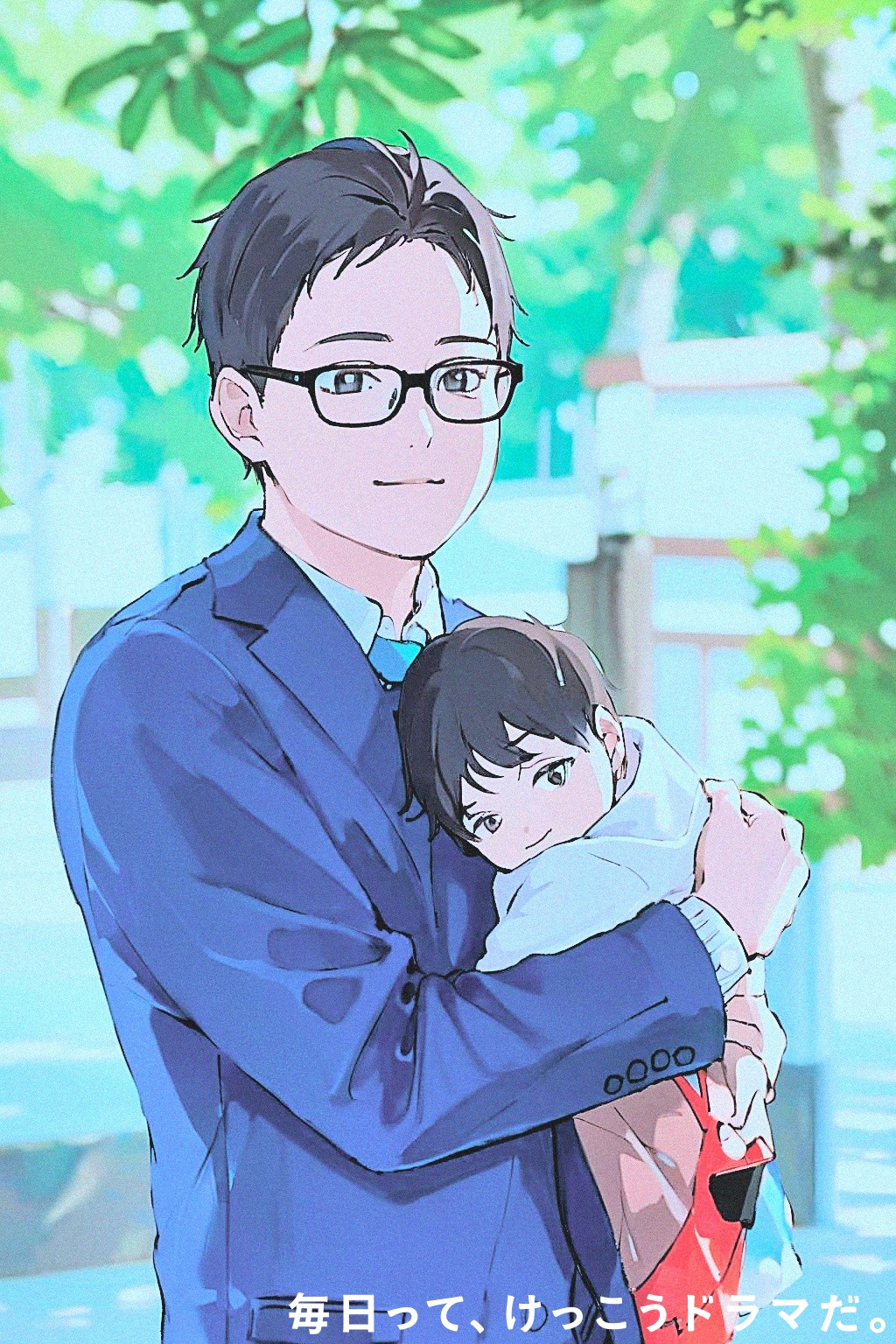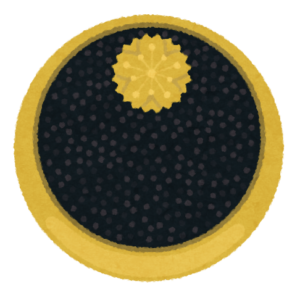租税教育推進部研修
私は支部において租税教育推進部を担当しています。租税教育とは小学校、中学校、高校、専門学校、大学などの学校の授業コマを使い、
税金についての講義を行うものです。
日税連のテキストの言葉を借りると、租税教育の目的は以下のようになります。
租税教育の目的は、「租税に関する意義、役割、機能、仕組み等の租税制度を知るとともに、申告納
税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し、社会の構成員としての正しい判断力と健全な納税者
意識を持つ国民を育成すること」です。
本日は租税教育推進部の栃木県のメンバーで、初めて講師を勤める方でも安心していけるような講義を行うという目的の元、研修を開催する側+参加する側、両方をやってきたという感じです。
各学校について、どんなコンセプトをもとに授業を組み立てるべきか、というのが私のグループで考えたテーマでした。
小学校:小学生の世界は周辺10メートルであることが多く、自身に関連するものから税金とは何かというファーストタッチを初めてあげることが重要。警察官、公園、学校など、税金からできている公共財について伝え、その公共財を維持するために税金が使われるということを伝え、誰かの税金のおかげで自分たちの幸せがあるというアプローチがいいのではないか。
中学校:小学生のときよりももう少し世界を広げ、どうすれば税金を「公平」に集めることができるか考えさせる。全員均等に、所得に応じて払う金額を決めさせるなど、考え方はいろいろあるが、100%正しい選択肢はない。所得税、固定資産税、消費税など、色々な税目を組み合わせることによって、最良な方法を見つけるべきというように、答えが一つに決まらないような問題を考えさせるアプローチがいいのではないか。
高校、専門学校:考え方は2極化する。所得の再分配やビルトインスタビライザーなど、税により顔の見えない誰かにどんな影響を与えるかというように、ミクロだった小学生の視点からマクロに考えを広げていくアプローチ、
もうひとつは高校卒業後すぐに役立つような実学を教えること。源泉徴収票の見方、所得税と住民税の関係など。中学まででだんだん広げてきた視野を集約させるようなアプローチ
最終的には学校との協議を重ねて授業の組み立て方を考えることになりますが、どんなコンセプトをもって授業を考えていくべきなのかが重要なことなんだと思いました。
とはいえ私はまだ実際に講師を経験したことはないので、早く座学だけでなく実際に自分で講師を担当したいなと思います。部担当の権限で1校くらい担当させてほしいなあ。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて
税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて 税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる
税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。
お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。 税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書
税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書