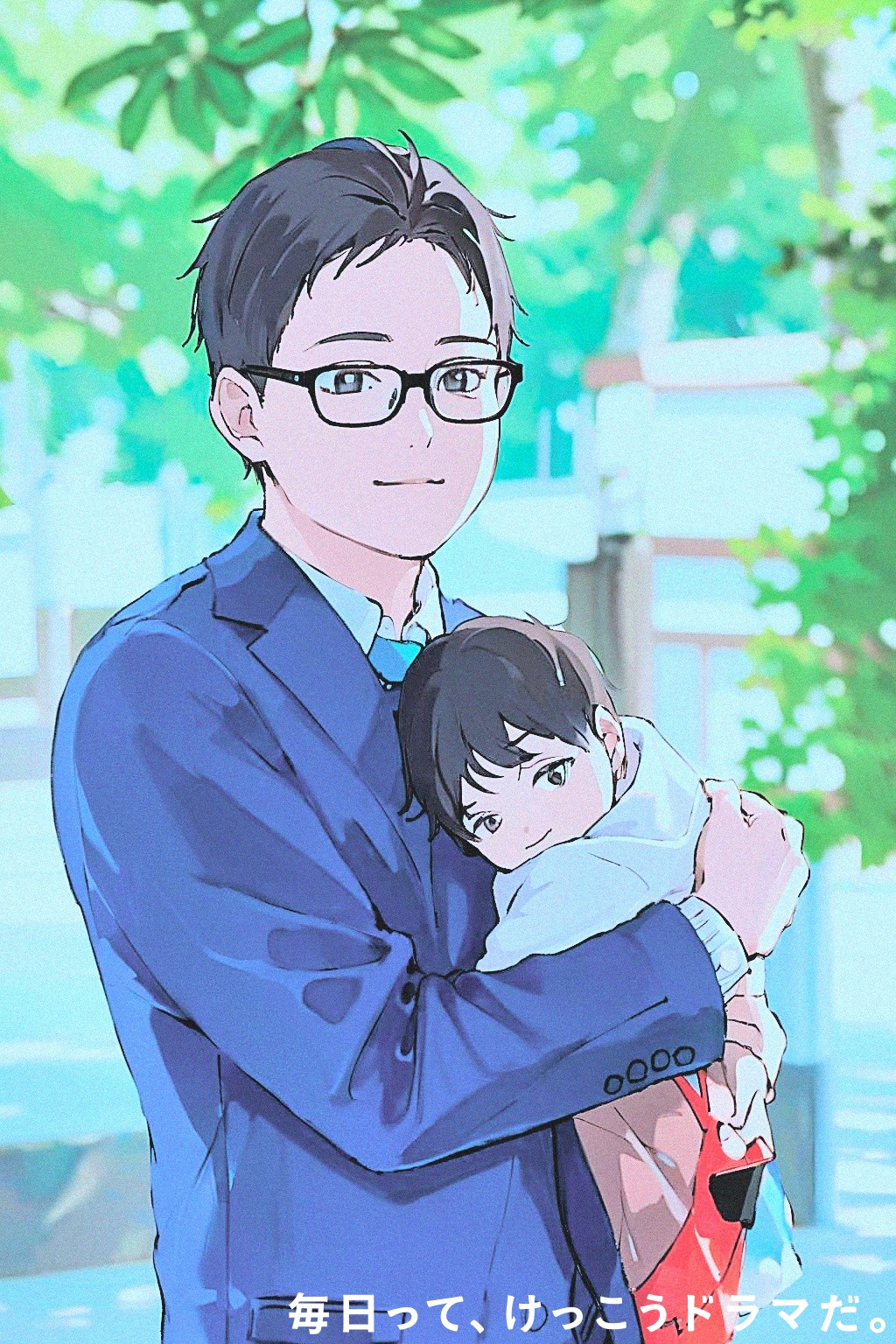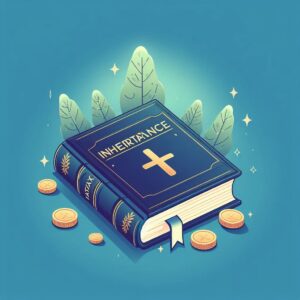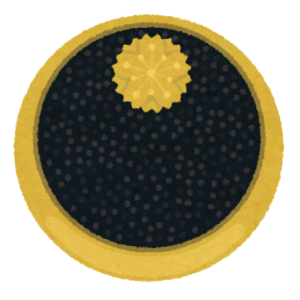住民税と所得税の「基礎控除」と「納税時期」の違い
はじめに
早いもので6月も下旬ですね。雨がなかなか降らずずっと暑いせいか体調を崩すことが多い月でした。
6月は手元に自動車税や住民税等の市県民税が届き始める時期です。特に住民税は去年の所得が今更関わってくるものなのでわかりにくいです。
住民税と所得税って何が違うの?という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。特に「基礎控除」や「納税時期」は混同されやすいポイントです。
令和7年度の税制改正を踏まえながら、両者の違いをまとめてみました。
1. 基礎控除額の違い【令和7年度改正対応】
| 税目 | 改正前の基礎控除額 | 改正後(令和7年分以降) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 一律48万円 | 最大95万円(所得に応じて段階的) | 合計所得金額が2,350万円以下の人が対象 |
| 住民税 | 一律43万円 | 変更なし | 所得税と異なり、控除額は据え置き |
ポイント: 所得税の基礎控除は段階的に引き上げられましたが、住民税は据え置きのため、両者に差が生じています。
また、サラリーマンが受けられる給与所得控除については最低額が55万⇒65万に引き上げられましたが、これについては住民税も同様です。
2. 納税時期の違い
| 税目 | 納税のタイミング | 納税方法 |
|---|---|---|
| 所得税 | 翌年3月(確定申告)または年末調整 | 給与から源泉徴収または確定申告で納付 |
| 住民税 | 翌年6月から翌年5月までの分割納付 | 給与天引き(特別徴収)または自分で納付(普通徴収) |
ポイント: 所得税は「今年の所得を来年3月に納める」のに対し、住民税は「今年の所得をもとに来年6月から納める」点が大きな違いです。
年末調整の方の場合、半年近くタイムラグがあるわけで、これはややこしいですよね。賦課課税であることも相まって、住民税がわかりにくい大きな理由の一つです。
3. 具体例で比較してみよう
例:年収200万円の会社員Aさん(独身)
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 合計所得金額 | 約132万円(給与所得控除後) | 所得税と同じ |
| 基礎控除額 | 95万円(令和7年度改正後) | 43万円(変更なし) |
| 課税所得 | 132万円 − 95万円 = 37万円 | 132万円 − 43万円 = 89万円 |
| 納税時期 | 令和8年3月(年末調整または確定申告) | 令和8年6月〜令和9年5月(住民税) |
結果: 同じ所得でも、控除額の違いにより課税所得が異なり、納税時期もずれます。
課税所得については特に大きくずれますね。所得税は370,000×5.105%=18,800円、住民税は890,000×10%=89,000円と、住民税の方が4.7倍ほど税額が大きくなります。
基礎控除額に大きな違いがあるのと、税率の違いですね。
まとめ
- 所得税の基礎控除は令和7年度から段階的に引き上げられ、最大95万円に。
- 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置き。
- 所得税は年末調整や確定申告で納付、住民税は翌年6月から分割納付。
今年からは特に、所得税はかからなかったけど住民税は1万以上かかる方が多くなりそうですね。社会保険料の壁も実質撤廃される見込みですし、
あまり壁を意識せず、突き抜けて働くのがいいのではないかなと個人的には思います。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて
税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて 税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる
税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。
お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。 税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書
税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書