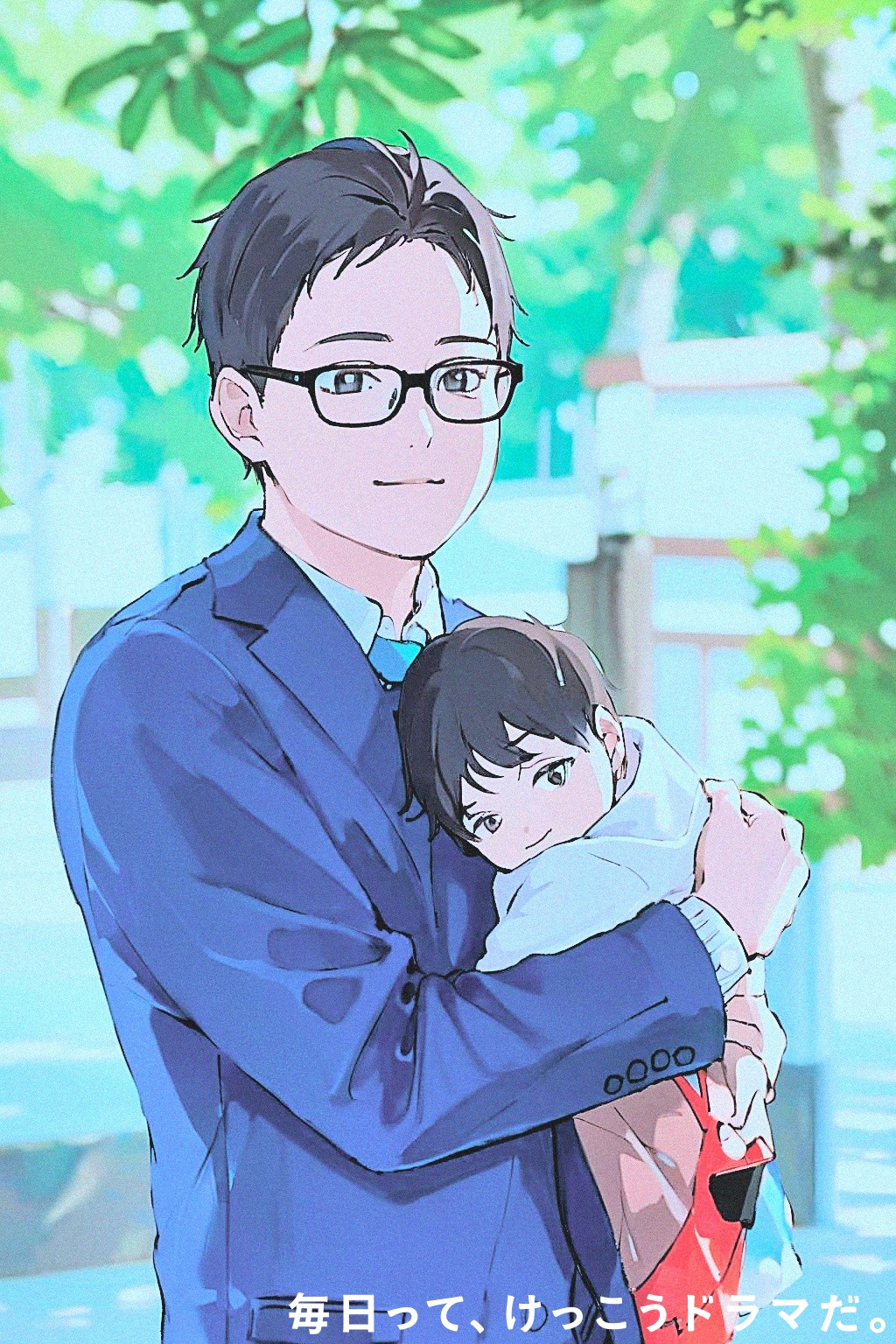8月の終わりに小規模宅地の特例に悩まされる
8月は申告業務自体は少なかったのですが、ありがたいことに新規契約となったお客様が複数あり、導入準備や租税教育推進部の会務でやはり忙しい月になりました。
6月から先は暇になるかな~と思っていましたが、結局開業してからず~っと忙しい状態です。
家事育児に時間を取られているのも原因の一つですが、思った以上に税理士の需要があり、本業が忙しいというのが大きな要因です。
1歳の子供が喋ってオムツが取れるまではゆっくりやろうと考えていたのですが、予想通りにはいかないものです。
でも、仕事が途切れずにあるというのは自営業者としては本当にうれしいです(サラリーマン時代はそうは思いませんでしたが)。
高い金を払って私に会社の根幹に係る情報を委託してくれたお客様の期待を裏切らないよう、これからも全力で仕事も家事育児も取り組んでいきたいと思います。
さて、そういうわけで、またクラウドワークス伝いで記事の監修業務を受けました。今回のテーマは小規模宅地の特例です。記事はこちら
https://www.all-senmonka.jp/souzoku/post/75327
せっかくなので大まかなまとめをこの記事でも書こうと思います。
🏡 小規模宅地の特例とは?
相続税の課税対象となる宅地について、一定の要件を満たすことで評価額を最大80%減額できる制度です。これにより、相続税の負担が大幅に軽減される可能性があります。
✅ 適用される宅地の種類
小規模宅地の特例は、以下のような宅地に適用されます:
| 区分 | 用途 | 減額割合 | 限度面積 |
|---|---|---|---|
| 居住用宅地 | 被相続人が住んでいた土地 | 80% | 330㎡ |
| 事業用宅地 | 被相続人が事業に使っていた土地(不動産貸付除く) | 80% | 400㎡ |
| 貸付事業用宅地 | 不動産貸付などに使っていた土地 | 50% | 200㎡ |
🏠 事例①:居住用宅地(同居の子が相続)
状況:
- 被相続人:父(死亡時85歳)
- 相続人:長女(独身・父と同居)
- 土地面積:200㎡
- 路線価:1㎡あたり40万円 → 評価額8,000万円
適用条件:
- 長女は父と同居しており、相続後も居住を継続
- 他に持ち家なし
結果:
- 評価額:8,000万円 × (1 - 0.8) = 1,600万円
- 相続税評価額が6,400万円減額
🧑🔧 事例②:事業用宅地(自営業の店舗)
状況:
- 被相続人:母(死亡時78歳・自宅で美容室を経営)
- 相続人:次男(美容師・母と同居し事業継続)
- 土地面積:300㎡
- 路線価:1㎡あたり35万円 → 評価額1億500万円
適用条件:
- 美容室は母の生前から事業として継続
- 次男が相続後も事業を継続
結果:
- 評価額:1億500万円 × (1 - 0.8) = 2,100万円
- 相続税評価額が8,400万円減額
🏢 事例③:貸付事業用宅地(アパート経営)
状況:
- 被相続人:父(死亡時82歳・アパート経営)
- 相続人:長男(別居・アパートは継続して賃貸)
- 土地面積:180㎡
- 路線価:1㎡あたり25万円 → 評価額4,500万円
適用条件:
- アパートは不動産貸付事業として継続
- 面積が200㎡以下
結果:
- 評価額:4,500万円 × (1 - 0.5) = 2,250万円
- 相続税評価額が2,250万円減額
💡 応用ポイント
- 老人ホーム入所中でも適用されるケース:自宅が空き家でも、要介護で入所していた場合は居住用宅地として認められることがあります。
- 複数の宅地がある場合:居住用+事業用など、組み合わせて適用できるケースもあります(限度面積の合計に注意)。
✍️ まとめ
小規模宅地の特例は、相続税対策として非常に有効ですが、要件を満たさないと適用されません。事前の確認と専門家への相談が重要です。
簡単に書くと上記のようになるのですが、実務としての相続税の案件に取り掛かってるときに悩むのは、小規模宅地の特例が使われる面積をどこからどこまでにするか、ということです。
同じ地番の土地でも、居住や事業の用に供されてる部分と、別に判断しなければいけない部分などがあり、上記で簡単に書きましたが対象面積を出す、というのが至難の業です。
私は相続専門の税理士ではないので、資産税特化型の先生にお金を払ってアドバイスをいただきながら相続評価をする、というのが多いです。
いつか特化型の先生と対等に話せるような知識と自信をつけたいものです。
現時点でも相続税の案件は抱えているので、お客様に損をさせないよう引き続き頑張ります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて
税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて 税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる
税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。
お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。 税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書
税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書