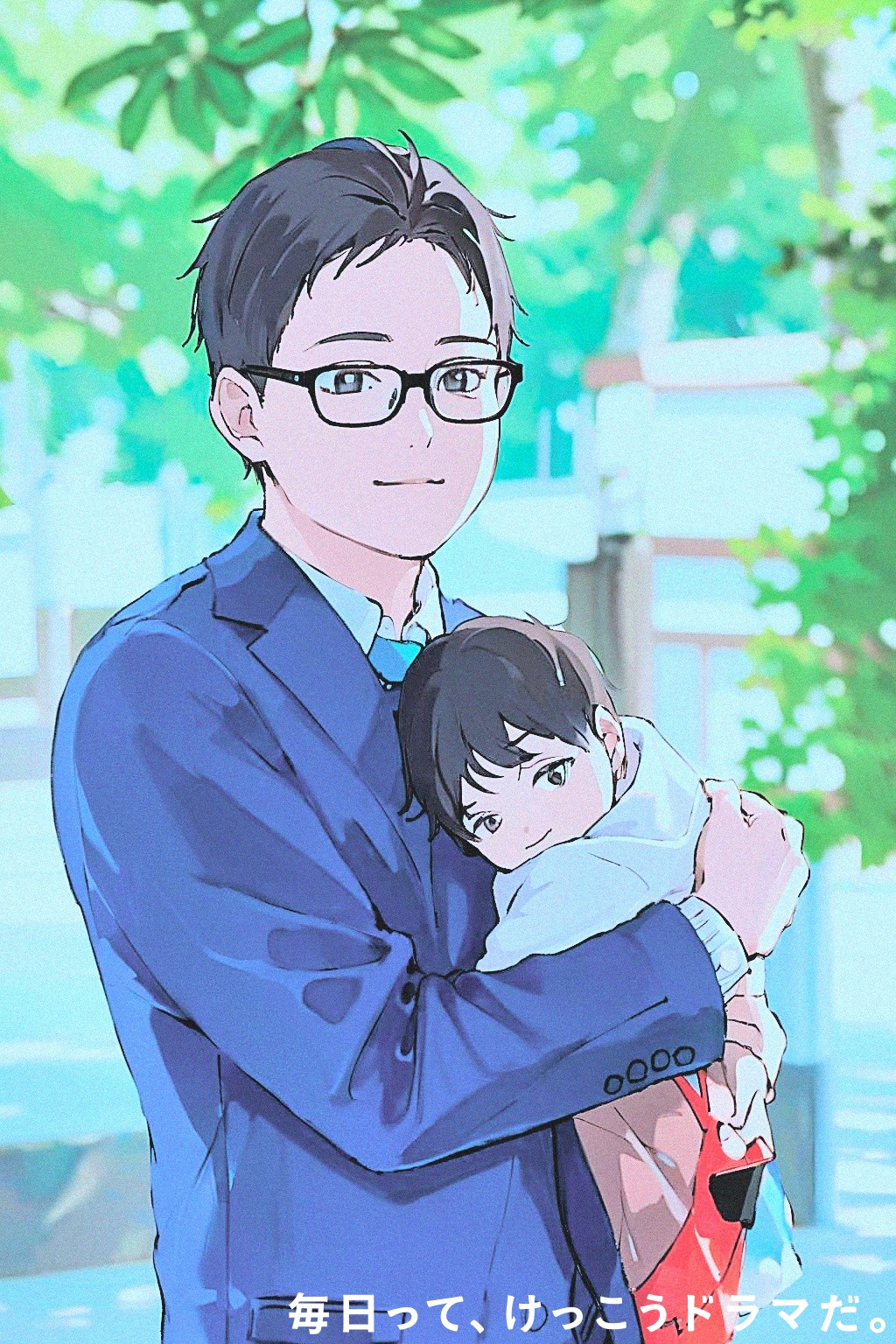R6.4.1開始法人から適用となる賃上げ税制
5月は3月決算の会社の申告月であるため、税理士は最後の繁忙期です。これをぬけたら12月くらいまでそんなに忙しくない月が続くのですが、
3月決算というのは事業年度が4月から始まるという事で、各種の税制改正の効果を良くも悪くも受けやすいです。私の顧問先でも何件か適用があったので、今回は賃上げ税制についてとりあげたいと思います。
令和6年度賃上げ促進税制
はじめに
令和6年度の税制改正により、企業の賃上げを促進するための税制が強化されました。令和6年4月1日以降に事業を開始する法人が対象になります。ちなみに個人事業主でも使うことができます。
賃上げ促進税制とは?
賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を一定割合以上増加させた場合に、法人税の税額控除を受けられる制度です。これにより、企業の賃上げを後押しし、経済の活性化を図ることが目的とされています。
適用対象
この税制は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される事業年度の法人が対象となります。また、青色申告書を提出している法人であることが条件です。
税額控除の内容
企業が前年度比で給与等支給額を一定割合以上増加させた場合、増加額の一部を法人税額から控除できます。具体的には以下のような控除率が適用されます。
- 基本控除率:給与等支給額の増加率が3%以上の場合、増加額の15%を控除
- 上乗せ控除:教育訓練費の増加などの追加要件を満たす場合、控除率が最大40%に拡大
・・・とはいえ、この税額控除、法人税額の20%が限度です。
例えば中小企業で所得600万の法人の法人税(国税たる法人税)は、600万×15%=900,000円ですが、900,000×20%=180,000円までしか控除は受けられません。なので、案外受けられる控除額は小さいという印象があります。
繰越控除とは?
令和6年度の税制改正により、賃上げ促進税制の繰越控除が導入されました。これは、法人税額の控除上限を超えた分について、最大5年間繰り越して控除できる制度です。
上記のとおり、法人税の20%までしか税額控除は受けられず、給与を増加しても十分な控除を受けられませんでした。この受けられなかった控除分を翌期以降に回すことができるようになったのが大きな改正です。
繰越控除のポイント
- 法人税額の20%を超えた控除額は、翌期以降に繰り越し可能。
- 最大5年間にわたり、未控除分を繰り越して適用できる。
- 繰越控除を適用するためには、明細書の添付が必須。
具体例
例えば、ある企業が令和6年度に給与総額を1億円から1億500万円に増加させた場合、増加額の15%(75万円)が法人税額から控除されます。しかし、法人税額の20%を超える部分については今期は控除は受けられず、翌期以降に繰り越して控除することが可能です。
申請方法
この税制を適用するためには、企業は適用年度の確定申告時に必要な書類を提出する必要があります。特に、繰越控除を適用する場合は、毎期明細書の添付が必須となるため、注意が必要です。
また、繰越控除を使うためには、それを使う期が、前期と比べて給与支給額が増えていることが要件となります。
給与総額を操作して、1期ごとに上げたり下げたりを繰り返すような場合は繰越控除を受けられない可能性が出るという事になりますね。というかそれを防止して、継続的な賃上げを行わせるためかと考えます。
まとめ
賃上げ促進税制は、企業の賃上げを支援し、従業員の所得向上を図るための重要な制度です。特に、繰越控除を活用することで、法人税の負担を軽減しながら、長期的な賃上げ戦略を実現できます。ぜひこの制度を活用し、企業の成長と従業員の満足度向上を目指しましょう。
賃上げ税制のような租税特別措置法は、使えるかどうかの検証が必要なので、税理士の腕の見せ所です。失敗すれば賠償責任にもなりうるため、注意しながらやっていこうと思います。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて
税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて 税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる
税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。
お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。 税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書
税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書