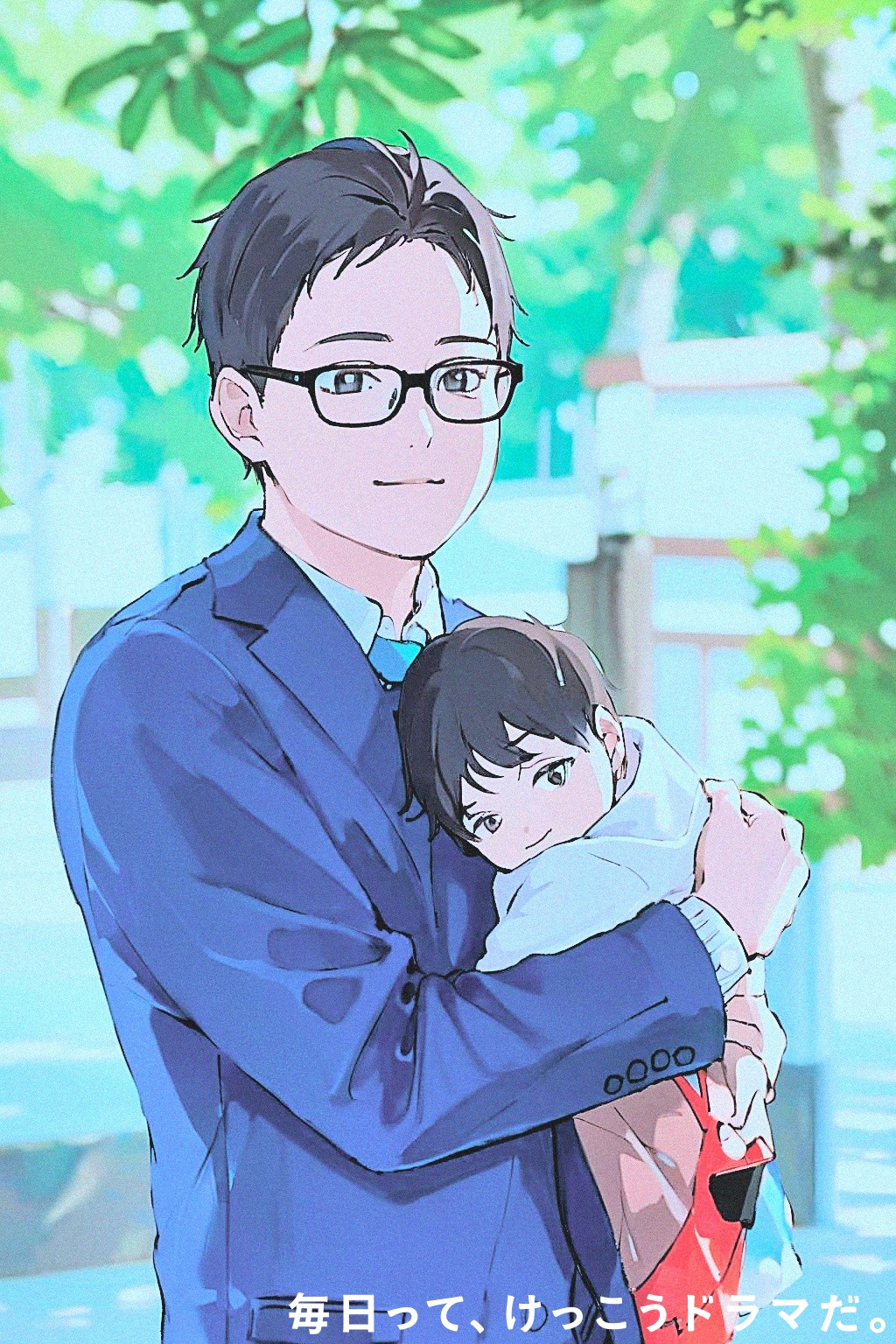個人事業主の売上金の使い方の注意点
個人事業主が受け取る売上に含まれる税金と社会保険料について
はじめに
サラリーマンのころは給与から勝手に社会保険料、所得税、住民税等の租税公課が引かれて残りの額が通帳に入っていたので好き勝手使うことが可能でした。私も若い時、ボーナスが入った次の日に同期とパチンコに行って10万円負けたりしましたが、おかげさまで税金滞納はせずに済みました。
しかし、個人事業主として活動していると、売上を受け取るたびに全額が口座に振り込まれます。実際にはその売上の中には所得税や住民税、社会保険料など、後で支払わなければならない費用が含まれています。この記事では、売上の中に含まれる税金や社会保険料の割合と、全額を使わないようにする理由について説明します。
売上に含まれる税金と社会保険料の割合
例えば、年間の売上が500万円の場合を考えてみましょう。この売上に対して、所得税、住民税、社会保険料がどれくらいかかるかを計算してみます。
- 所得税:
- 所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど税率が高くなります。
- 仮に所得税率が20%だとすると、500万円の売上に対して100万円の所得税がかかります。
- 住民税:
- 住民税は一律の税率で課税されます。
- 住民税率は10%なので、500万円の売上に対して50万円の住民税がかかります。
- 社会保険料:
- 社会保険料には国民健康保険料や国民年金保険料が含まれます。
- 国民年金は年額約20万円、国民健康保険料はさくら市だと概ね10%ほどであり、500万円の売上に対してだと50万円ほどになります。。
税金と社会保険料を考慮した売上の管理
上記の例では、500万円の売上に対して100+50+20+50=220万円の税金と社会保険料がかかることがわかります。つまり、実際に自由に使える金額は300万円ほどとなります。今回の計算では所得控除や事業の経費などを全くみていないので、税額はこれより小さくなるはずです。
しかし、このように入金額の中には支払うべき租税公課が含まれていることは意識しなければなりません。売上や所得が一定以上になると消費税や事業税もかかることになるのでより一層気を付けなければなりません。
具体的な対策
- 税金と社会保険料分を別口座に分ける:
- 売上を受け取ったら、税金と社会保険料分を別の口座に移しておくことで、後で支払う際に困らないようにします。
- 定期的な税金と社会保険料の計算:
- 毎月や四半期ごとに税金と社会保険料を計算し、必要な金額を確保しておくことで、年度末に大きな負担を感じることなく支払うことができます。
- 税理士に相談する:
- 税金や社会保険料の計算や管理に不安がある場合は、税理士に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。
結論
個人事業主としての売上には、所得税や住民税、社会保険料などの費用が含まれていることを理解し、全額を使わないようにすることが重要です。適切な管理を行うことで、安心して事業を続けることができます。
とはいえ、事業は売上金を仕入等の次の投資に回していき、だんだんと拡大させていくのが常です。わかっていても税金分を残すというのはなかなか難しいですね。
ただ、あとで租税公課が待ち構えていることを覚悟しているのとしていないのでは対策の取り方が違います。頭の片隅に置いておくことは必要だと思います。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて
税理士業務2026年2月7日租税教室を終えて 税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる
税理士業務2026年1月31日1月が終わって2月が始まる お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。
お知らせ2026年1月22日「はじめての税金講座」の講義を行ってきました。 税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書
税理士業務2026年1月9日1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書